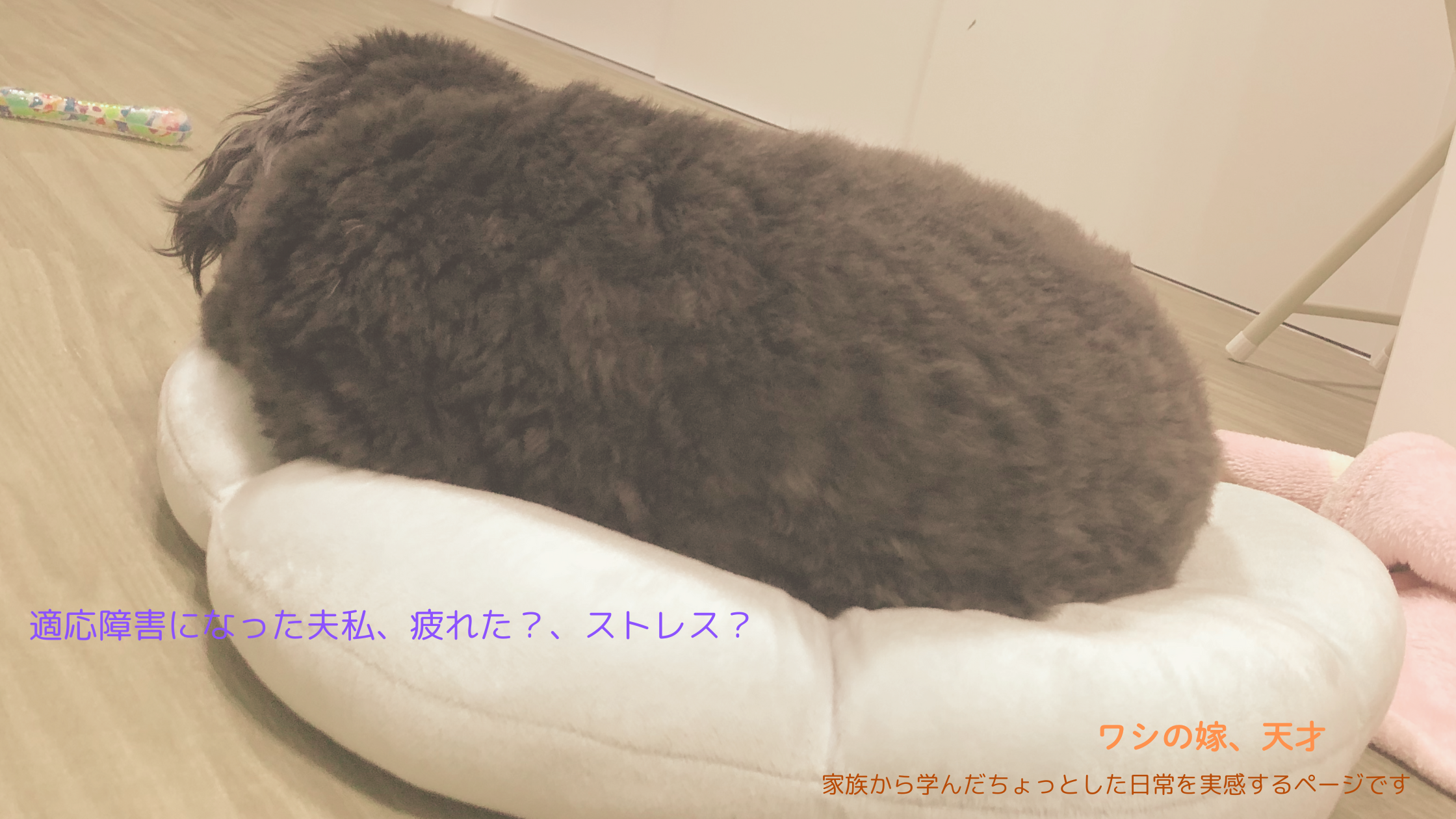現在休職中の夫私が家族から受けた名言などをまとめています。
今回は出勤できなくなった時に感じた疲労感を少し掘り下げて勉強してみました。
疲労ってなんなんでしょうね。
今回参考にさせていただいた本は近藤一博先生の著書、「疲労とはなにか」講談社BLUE BACKSです。この本を読むことでなんとなくわかった気になっていた疲れが本当は全く違うメカニズムで起こっていたことを知ることができました。
本当に救われて気分になりました。

message
0) 疲労(疲労感の原因となる体の障害や機能低下)と疲労感(疲れた、休みたいという気持ち、休養の願望)は異なる
1) 疲労には生理的疲労と病的疲労がある
2) 生理的疲労は体内のどこかしらで発生した炎症による炎症性サイトカインが脳に伝わり生み出される(脳が炎症しているわけではない)
3) 生理的疲労には睡眠や食事など生活習慣の改善と軽負荷の運動(歩行など)が効果的
4) 代表的な病的疲労に慢性疲労症候群やうつ病がある
5) 病的疲労は脳内で炎症が起こっている
6) 脳内炎症を消火するコリン作動性抗炎症経路が、アセチルコリンの低下により作動できないため、疲労感が長期化する
7) 生理的疲労と病的疲労は脳内炎症が起こっているか否か
8) 生理的疲労が過度に強くなると病的疲労に移行することがあり、唾液中のHHV-6を測定すればどちらの疲労かがわかる
ストレスとは?
以前の記事の「休養学」でも触れましたが、ストレッサーの分類を再度列挙してみます。
| ストレッサー | 具体例 |
| 物理的ストレッサー | 暑さ、寒さ、騒音、混雑、振動 |
| 化学的ストレッサー | 公害、薬物、化学物質 |
| 心理的ストレッサー | 不安、緊張、怒り、悲観 |
| 生物学的ストレッサー | 細菌、感染、ダニ |
| 社会的ストレッサー | 家族関係、友人関係、人間関係 |
上記の内容をちょっと異なった視点、切り口から分類するのものあります。
| 労働、訓練などの負荷 | アミノ酸不足 | ウイルス感染 | 酸化ストレス | 小胞体ストレス |
体の中や細胞レベルなどでストレス分類すると、ちょっと難し表現になるみたいですね。「小胞体ストレス」などはタンパク質合成の際、折りたたんでいく作業でエラーが生じた場合がこれに該当するようです。
このような様々なストレッサーがどのようにして疲労感につながっていくのでしょうか。
疲れた?疲労とは?
疲労の定義を再度、検討してみます。日本疲労学会が定義する疲労*1)とは、
「過度の肉体的及び精神的活動、または疾病によって生じた独特に不快感と休養の願望を伴う身体の活動能力の減退した状態である」
としています。この定義では一般的に解釈されている疲労状態を記載されていると思います。
*1)休養学 p.46、片野英樹著、東洋経済新報社
ではストレスと疲労の関係を考慮するとどのように定義すれば良いのでしょうか。一般的な「疲労」には2つの意味が含まれていると思います。疲れたという感覚である「疲労感」と、疲労感の原因となる「体の障害や機能低下」です。ストレッサーが疲労感につながっていく経過をたどると以下のような定義がしっくりくると思います*2)。
疲労:疲労感の原因となる体の障害や機能低下
疲労感:「疲れた、休みたいという気持ち、休養の願望」
痛みと同じように生体アラーム信号
*2)疲労とはなにか、P.29-30、近藤一博著、講談社BLUE BACKS
そして疲労は2種類に大別されます*3)。
生理的疲労:仕事や運動などで発生し、1日休めば回復するような短期的な疲労病的疲労:何ヶ月も続き、少々休んだぐらいでは回復しない疲労
*3)疲労とはなにか、P.31、近藤一博著、講談社BLUE BACKS
それでは疲労とはどのようなメカニズムで疲労感につながっていくのでしょうか。
生理的疲労とは
普段よく耳にする疲労に近いものがここに該当するような印象です。また疲労しているかどうかは唾液中のヒトヘルペスウイルス6(HHV-6)の増加である程度予測はできるようです。
さて著書によると疲労のキーワードは炎症のようです。また生理的疲労の状態にある時、唾液中にHHV-6の量が増加しているようです。生理的疲労では「体のどこかしら(末梢性)で生じた炎症性サイトカインが脳に伝わり疲労感を引き起こしている*」とのことです。確かに様々な慢性疾患の原因に炎症が絡んでおり、慢性疾患の特徴に疲労感・倦怠感がよく列挙されているのも頷けます。
ただし脳内で炎症は生じていないのが生理的疲労と病的疲労の大きな違いとのことで、疲労が比較的短期間の休息で改善するのもこの点が重要なのかと思いました。
*疲労とはなにか、P.33、近藤一博著、講談社BLUE BACKS
では疲労を改善させるにはどのような方法があるのでしょうか。
よく言われているのが睡眠や食事の改善ですが、軽度の疲労を加えると生理的疲労の改善につながるメカニズムが簡潔にご紹介されていました。
軽度の疲労、すなわち運動することで疲労に対する回復力が高まるということがわかり、生理的疲労の減少につながることがわかった*とのことでした。
確かに週末、子供達と公園に出かけたり、何かしらのレジャーを楽しんだ時は、筋肉痛など生じたとしても全身の疲労感はあまり感じられなかったような気がします。
*疲労とはなにか、P.69、近藤一博著、講談社BLUE BACKS
また私が今回体験したであろう俗に言うストレスも疲労感に対してはあまり効果的ではないようです。しかし解釈は私が思っていたものとは異なっており、まさに目から鱗でした。
一般的な精神社会的、肉体的なストレスでは視床下部ー脳下垂体ー副腎皮質軸(HPA軸)を活性化することは様々な書物でも言われています。副腎皮質ホルモンの分泌が促されますが、このホルモンは強い炎症抑制作用を発揮します。
精神的ストレスを感じた時はかなりの疲労感を感じたのですが、炎症抑制作用が発揮されれば疲労感の改善につながるはず、あれ、おかしいと思いました。
著書ではさらに、「この時同時に視床下部は交感神経も刺激して副腎髄質からアドレナリンやノルアドレナリンを分泌させ興奮作用を及ぼす*」とのこと。
つまり副腎皮質ホルモンで疲労の原因となる炎症を抑制し、交感神経の刺激も興奮作用のため疲労感を軽減させてくれる。確かに明日までにしなければいけないことがあった時などこの作用のおかげで何度も助けられた記憶が呼び起こされます。
そうです、この作用は短期的には進化の過程でもかなり有効に働いてくれました。しかしこのストレスが長期にわたると疲労は蓄積するため気づいた時にはかなり進行した状態になっているわけです。
おそらく出勤できなくなった時期はこのような状況だったと思います。
*疲労とはなにか、P.51-53、近藤一博著、講談社BLUE BACKS
病的疲労とは
今までは生理的疲労を見てきましたが、もう一つの疲労、病的疲労とはどのような状態なのでしょうか。
代表的な病的疲労の疾患に慢性疲労症候群、うつ病などがあります。慢性疲労症候群では生理的疲労にみられた唾液中のHHV-6の増加が見られません。そして生理的疲労とは異なり脳内で炎症が見られます。
ではどのようにして脳内に炎症が起こるのでしょうか。
実はその内容はかなり複雑で自分なりに流れを図にしてみたのですが、誤りあるといけないので割愛させていただきます。
病的疲労の状態では脳内の炎症抑制経路が障害*され、末梢からの炎症性サイトカインに作用できず脳内炎症に至ってしまうようです。脳内炎症の影響はその病名からもわかるように日常生活にも支障をきたしかねない状況だと思われます。
*疲労とはなにか、P.174-175、近藤一博著、講談社BLUE BACKS
生理的疲労から病的疲労への移行*もあるとのことで、生理的疲労に耐えている間に徐々に脳内炎症をきたしていく過程を想像すると、的確な判断ができない状態に知らず知らず進行してしまうのだろうと思いました。
*疲労とはなにか、P.213、近藤一博著、講談社BLUE BACKS
私は日々続く疲労感を感じながら耐えてきましたが、突然のパワハラ行為に心がポキっと折れたのを感じることができました。ある意味、幸いだったのかもしれません。
最近、レジリエンスという言葉をよく聞きます。それについてもまとめているのですが、休職してから10ヶ月が経ち、いろいろ振り返りながら立ち直ろうと、本当に半歩ずつ進んでいるかいないか、とういう状況です。
今後はさらに他のジャンルを勉強しながらもっと深く自分を理解したいと思っています。